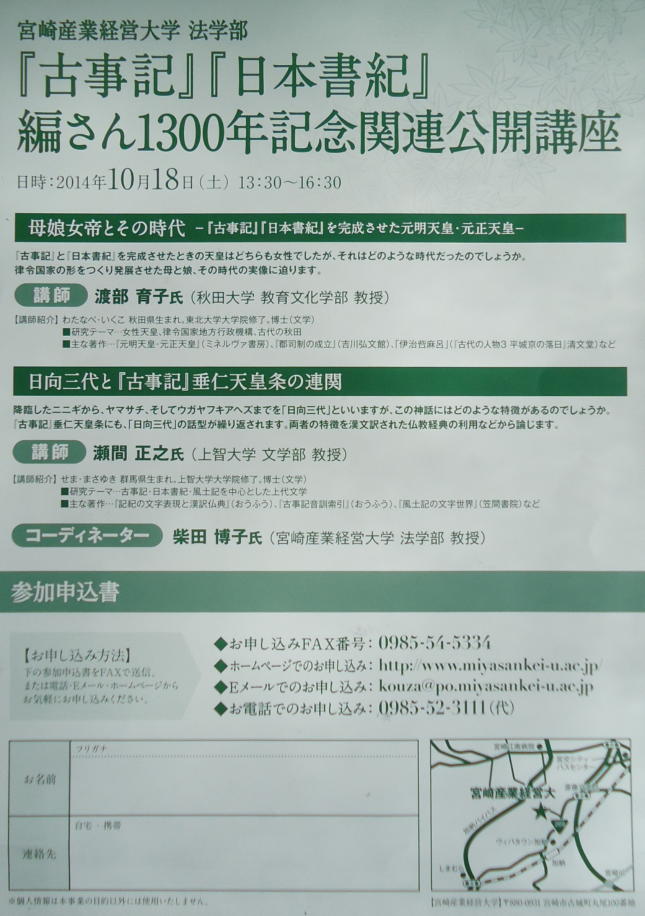< 仏教と古事記・日本書紀 >

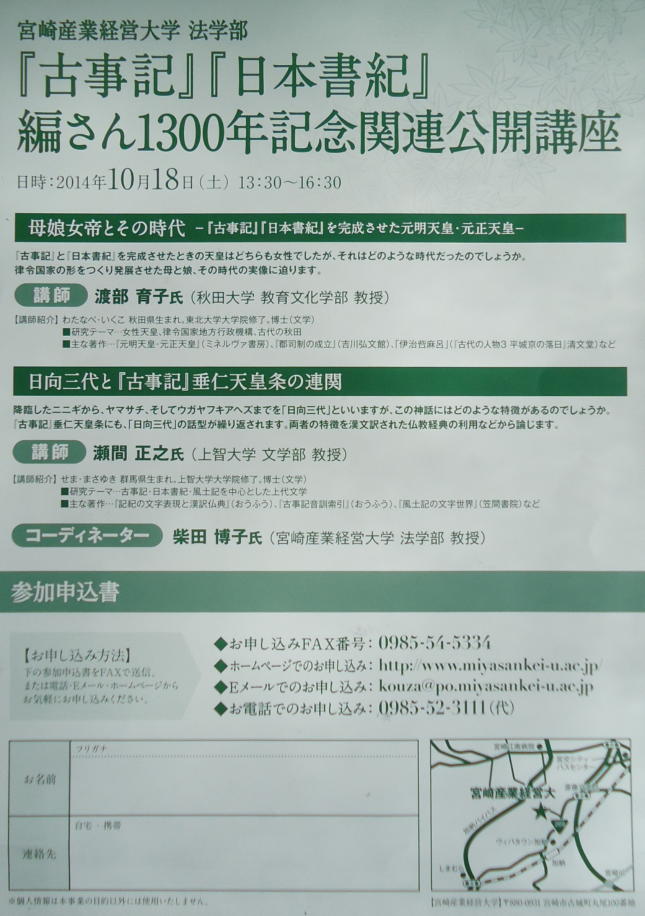

(宮崎産業経営大学)

(渡部育子氏)

(瀬間正之氏)
< 経律異相 >
梁の武帝の勅命により、天監7年(508年)に僧旻が撰集し、再度勅命によって、天監15年(516年)に宝唱が主となり、僧豪・法生等の助力を得て増補改編した全50巻の一種の類書である。
< 経律異相 > |
< 古事記 ><日本書紀> |
| 兄弟の争い |
◎ ◎ |
| 案内の老人 |
◎ ◎ |
| 教えの通り到着 |
◎ |
| 宮の描写 |
◎ ◎ |
| 婢の取次 |
◎ |
| 王女との結婚 |
◎ ○ |
| 歓待される |
◎ ○ |
| 宝珠を受ける |
◎ ◎ |
| 還国して王になる |
○ ○ |
| 兄弟が守護となる |
◎ ○ |
< 法華経 >
最終的にこの神話が記定された段階を中心とするところの古代の知識人が関心をもったという点から言うならば、さらに逸することができない一つの事実がある。それは、当時の文字ある階級の人々が本章の所伝内容を知った時に、必ず思い合わせずに居られなかったはずのものとして、『法華経』の所説があったということである。この両者の所説の間に思い合わせられるものの多いことは、すでに本居宣長が、
『仏書に竜宮と云う物あり、其ノ説るさま、あやしきまで此ノ段にいとよく似たる処あり、故レ書記の口決纂疏などには、此ノ海ノ神ノ宮を、直に竜宮とぞ云れたる、仏書を信める人は、然主客の語を別(ワキ)まへだになくて、彼ノ所謂竜宮を、主として云れたるなり』
と指摘している。宣長は、皇国書を中心とするたてまえから、
『仏書の竜宮は、此ノ綿津見ノ神ノ宮の事の、上代におのづから、天竺などにも、かたはし伝はりたるに、種々の事を造リ加えて説たるものなり、又漢ぶみにも似たる事のあるも、然なり』
と強弁せざるを得なかったのであるが、それにもかかわらずこの段の古事記の本文に「益我王而甚貴」とある「我王」を注するにあたっては、
『伎美と云に、王ノ字を書るは、仏書の海竜王を思へるや、こは皇国を離れて、外なる域なれば、王と云まじきにも非るが如くなれど、なほ古文には、かかる処には、いかがなる文字づかひなり、書記にも、我王また其王など書れたり』
と漏らしているのである。そしてここに示された見解こそは、最も自然なものであったと言えるのである。
『法華経』がわが国に伝来したのは、恐らく六世紀の後半の間のことであったろうが、いちはやく聖徳太子によって義疏撰述のことが為され、奈良時代に入ってからは、聖武天皇の神亀三年(726)に、太上天皇の奉為に釈迦像ならびに法華経を造写されたとあり、また天平六年(734)には、太政官の奏によって、僧尼の学業を奨めんがために、得度にあたって法華経一部あるいは最勝王経一部を暗誦し、浄行三年以上ならんものを取ることとされたとあり、さらに同十二年(740)には、国ごとに法華経十部を写し、ならびに七重塔を建てしめられたともあるのである。法華経に対する関心がいかにたかまりつつあったかを想像することができる。
このような背景事実とともに、古事記や古風土記が、その文体の形式において法華経に負うものをもっているという重大な事実があがって来るのである。この点は、神田秀夫氏によって明らかにされたところであるが、「法華経及び維摩詰の羅什訳が古事記及び風土記の文体に与えた影響は根本的なもので」あったと見られる。これらの事実をもととして、記紀撰修当時における法華経への関心を推測することは、少しも不自然ではないであろう。
かかる趨勢が確認されるとすれば、小論の主題である「海宮遊行章」の所伝内容に接した時人が、法華経提婆達多品の所説を思い合わせたとしても何ら奇異とすべきものはない。
① 文殊菩薩が大海の娑竭羅竜宮に往還されたという点。
② 竜王の女が竜宮を出て成仏したという点。
③ 竜女が一宝珠を仏に上ったという点。
など、むしろ、これとかれとを思い合わせなかったとする方が不自然だとも言える。唐突な「塩土老翁」の出現も、同品の「仙人」の出現を連想させたことであろう。
すでに上にも述べて来たように、「海宮遊行章」の本書は、豊玉姫が御子を産まれる時のこととして、「化為竜」と記している。この点について津田左右吉博士は、
『この竜がワニの転じたものであることは、いふまでもないが、海神の女が竜身を現じたといふのは、支那思想よりは寧ろ仏典に由来があるのではないか、とさへ疑はれる』
と説いて居られるが、この本書にあらわれた一徴候は、本章の記定者が法華経提婆達多品の所説を思い合わせていたことの証跡となるのではなかろうか。そのほか、本書における、彦火火出見尊が海神の宮の門前の下にたたずまれたとする辺の記載は、法華経宝搭品に、
『至娑婆世界、各到宝樹下、一一宝樹、高五百由旬、枝葉華果、次第荘厳、』
とあるのが思い合わされて然るべきであったであろう。また、鈎を兄に返す時の一種の呪文にしても、たとえば同経誓喩品に、
『生老病死憂悲苦悩愚痴暗蔽』
とあり、同安楽行品に、
『貧窮卑賤醜陋』
とあったりするようなものを連想せしめなかったとは言えぬであろう。
いかにも、『海宮遊行章』神話の素性については、南洋方面に相当広く伝承されている釣針借りの説話などと深い脈絡をもつものであって、決して法華経の所説から来たものではあるまいとは考えられるけれども、問題を記紀編集当時のことに移して考えると、それらの事業にたずさわった人々の思い合わせるところは、南洋諸島の釣針借りの説話ではなくて、法華経の所説でなければならなかったと言えるのである。
言うまでもなく、法華経の所説がもとになって『海宮遊行章』神話が生み出されたものとは信ずることができない。素材的には、由来の古い伝説説話が複合しているおもむきは、よく観取されるのである。けれども、そういうことを認めることと、記定者に法華経の所説が思い合わされたろうとすることとは、少しも矛盾するものではなかろう。そして、思い合わされたとするならば、記定者にそのことが何らかの意味をもって作用していたに相違なかろうと考えても不合理ではあるまいと考えられる。
(「日本書紀神代巻の一考察」太田善麿)